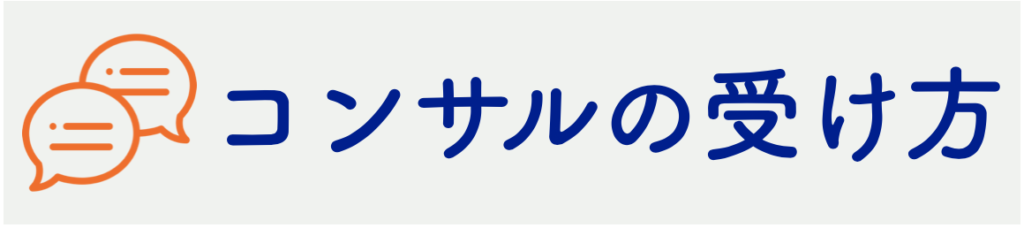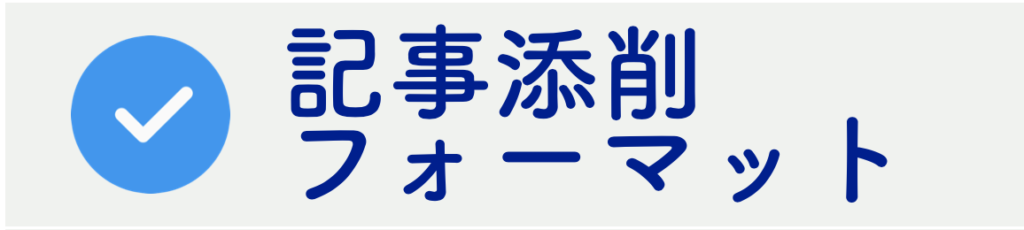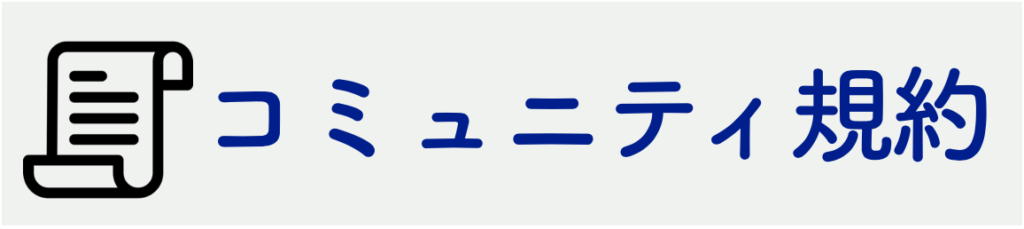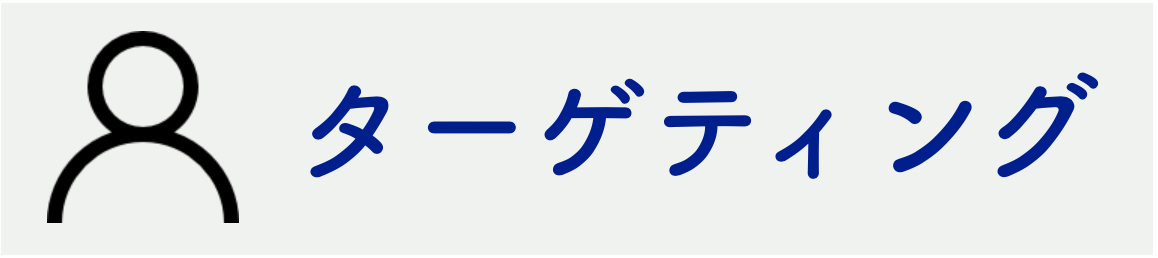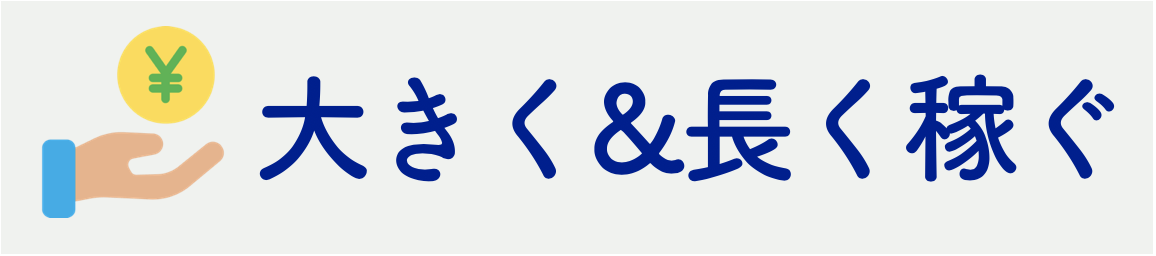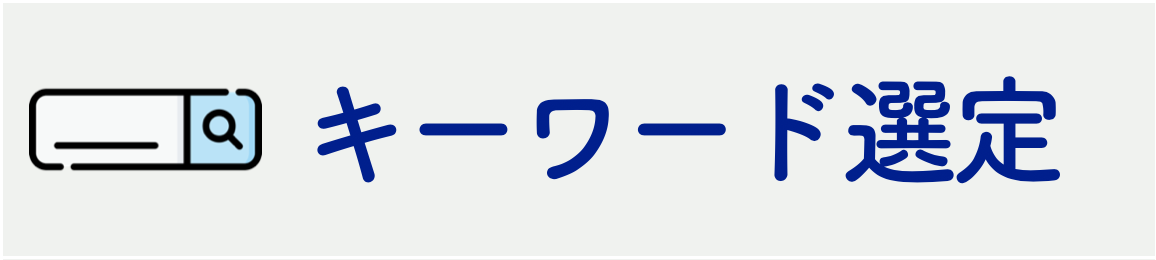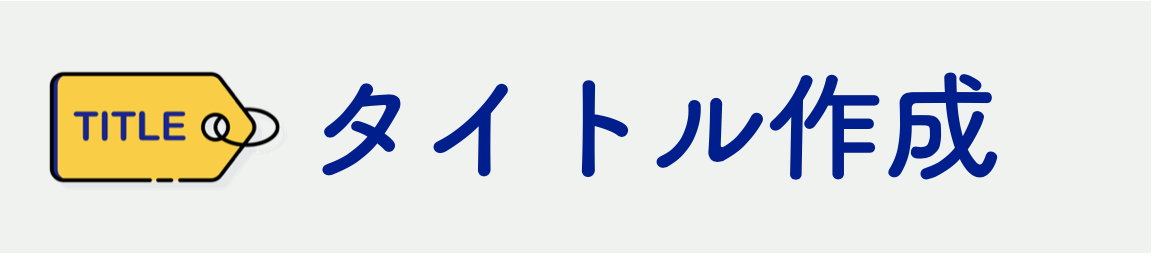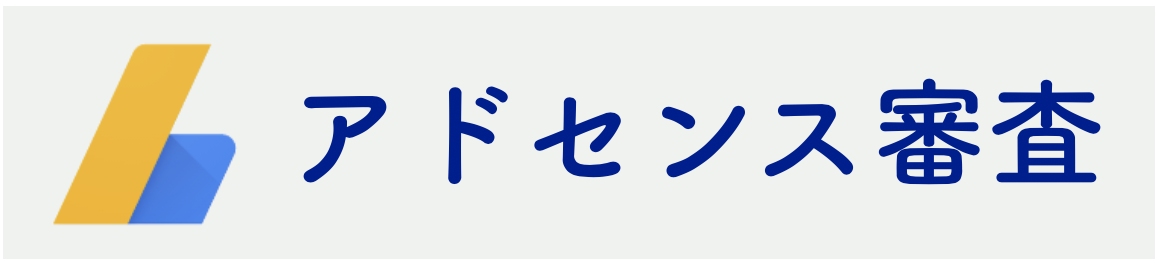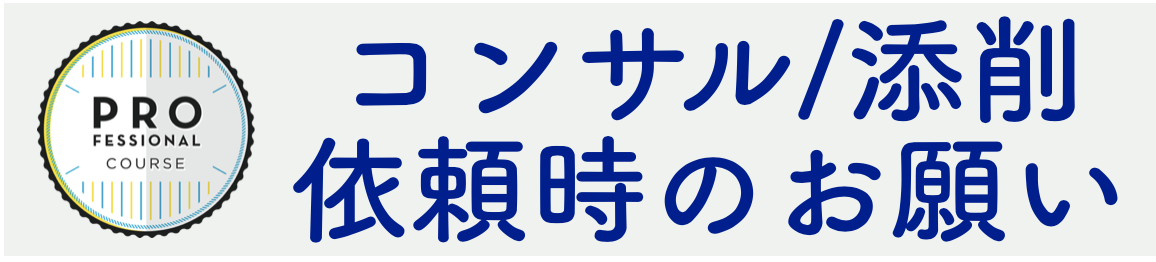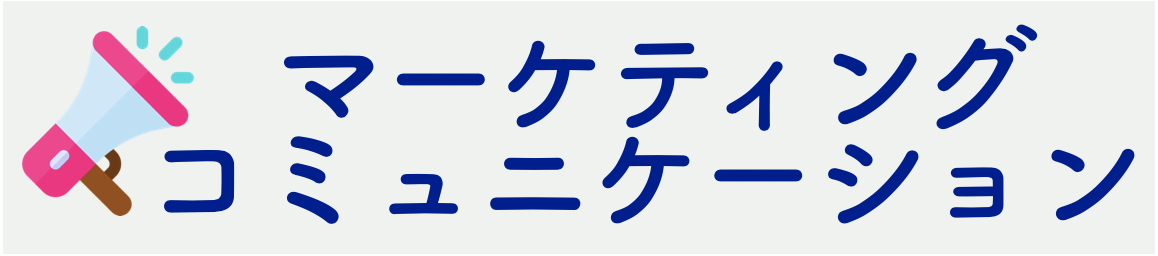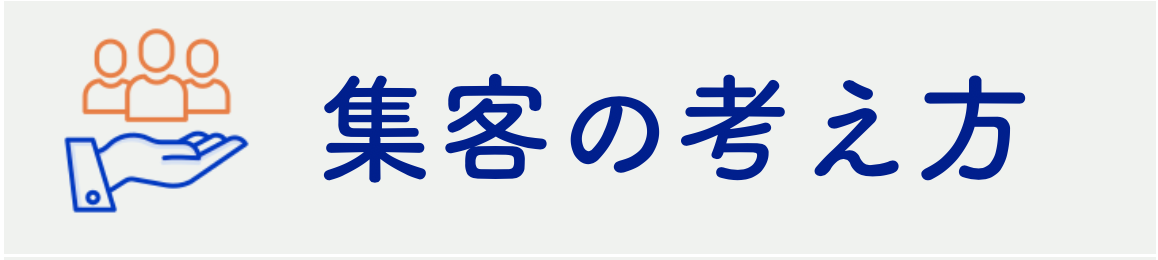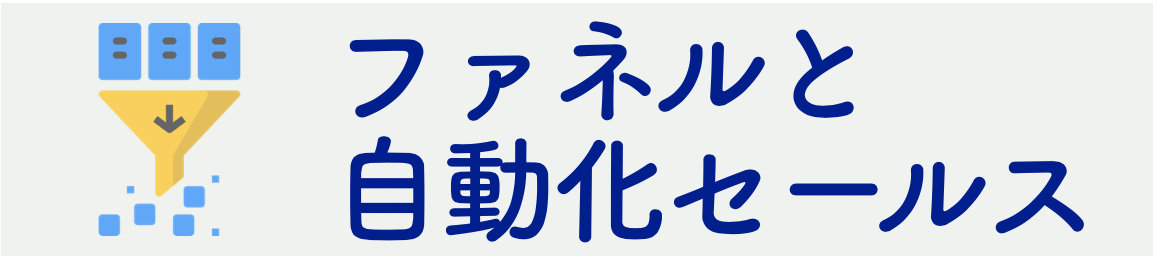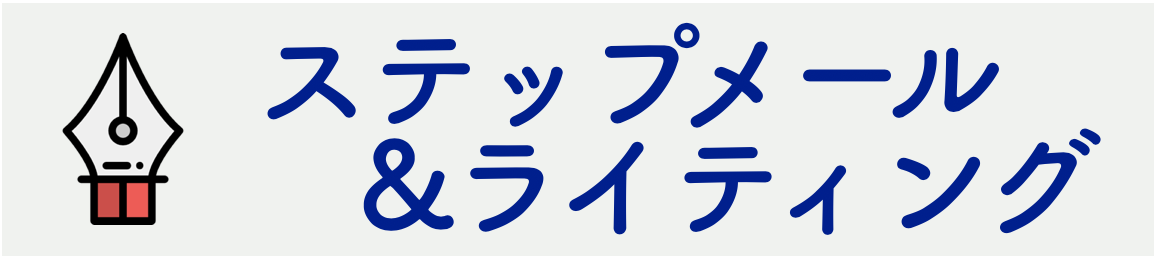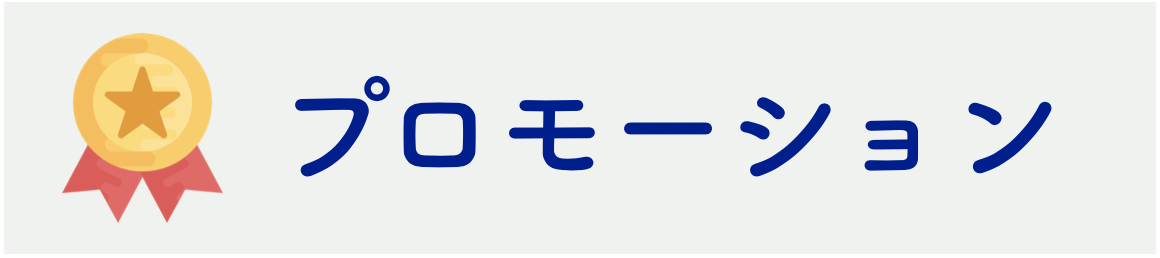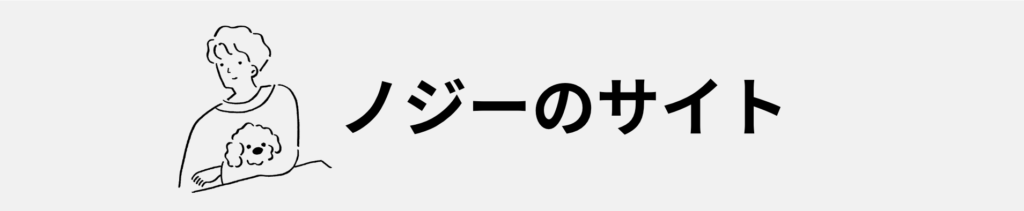これは僕が常々言い続けていることですが、何かアウトプットに問題がある時は「インプットに問題がある」と思った方がいいです。
例えば、「メルマガが上手く書けない」という人は、そもそも他の人のメルマガを全然読んでいなかったり、読んでいたとしても流し読みで、メルマガが上手い人のコンテンツを分析するということが全然できていなかったりするものです。
以前にも、僕がスポットのメルマガ配信をする度に「ここの表現はどういう意図で書かれたのですか?」とか「そもそも何でこのテーマで書こうと思ったんですか?」とか「敢えてこういう展開にされたのは、こういう意図があったからですか?」といった感じで質問攻めをしてくださる方がいましたが、彼はめちゃくちゃ伸びていきましたね。
ブログでも同様に、上手くいってる人のブログを読みまくってる人や、教材のインプット量が多い人は、アウトプットするときにもそんなに変なことにはなりません。
例えば、「ブログを書くのに時間がかかりすぎる」という人の作業の流れを聞いていても、教材で語られている基本的な知識が全然身についていなかったりするので、「そのやり方や理解度じゃ時間もかかるよね…」と思えてしまうことが往往にしてあるものです。
よく「守破離の原則」と言いますが、まずは「守ること」を徹底していくだけで普通に結果って出て行くものですし、結果が思うように出ない場合、添削で良い言葉が返ってこない場合(笑)は、まず徹底的に「守破離の守」の部分ができているのだろうかと省みることは大事ですね!
インプットも色んなところに手を広げるのではなく、まずは教材に書かれていることをフルで理解できるようになるまで、何度も何度も繰り返して学ぶくらいが丁度いいです。
色んなところからインプットをして消化不良になったり、あるいは「良いところどり」をしようとされる人もいるかもしれませんが、大抵の場合「自分にとって都合の良いところどり」になって終わるものです。
「学ぶ」は「真似ぶ」とも言いますが、まずは僕やYUMEさん、あるいは既に自分が目指す目的地点に到達している先輩メンバーと「同じようにできるようになる」ことであったり、自分で教材の内容を誰か他の人に完璧に教えられるようになることを目指していかれるといいですね。
ということで、3連休の真ん中にちょっと重めなコラムですが、アウトプットに問題がある時はインプットに問題がある、という原則をぜひ抑えていただければ幸いです!