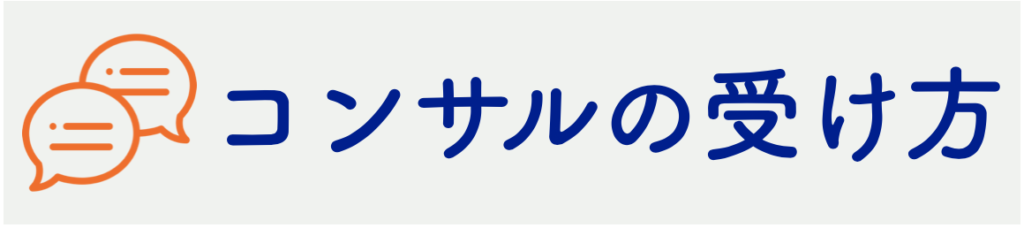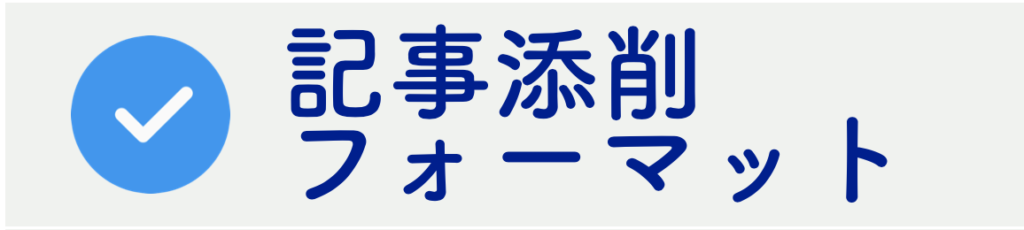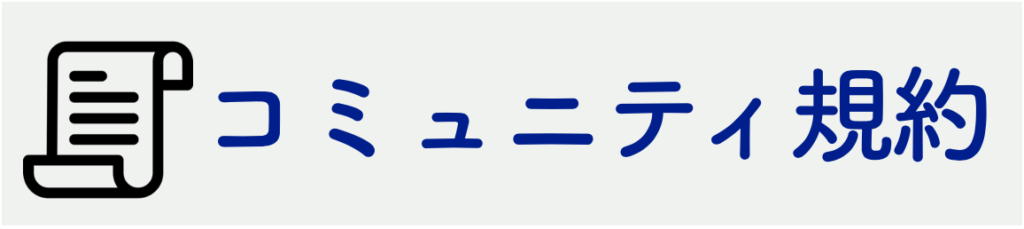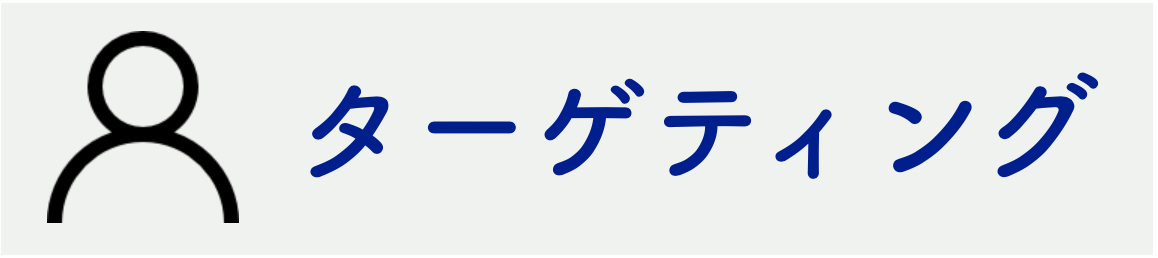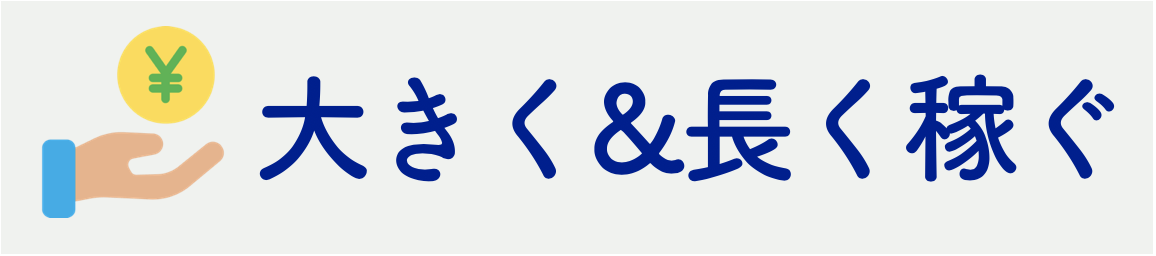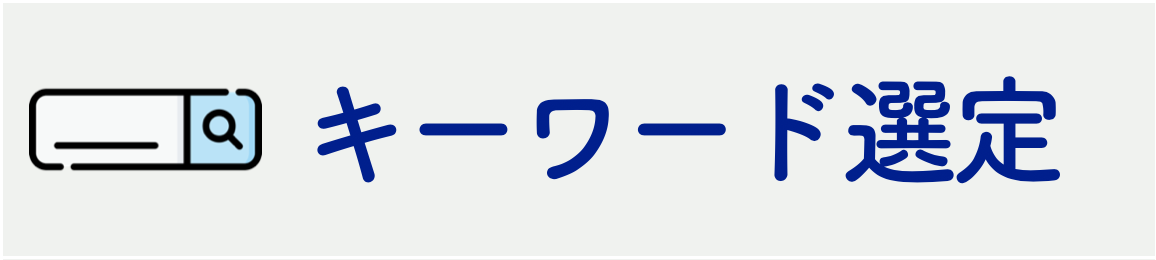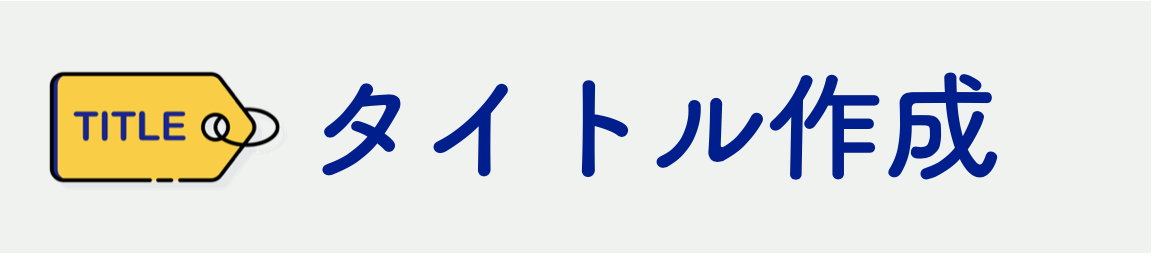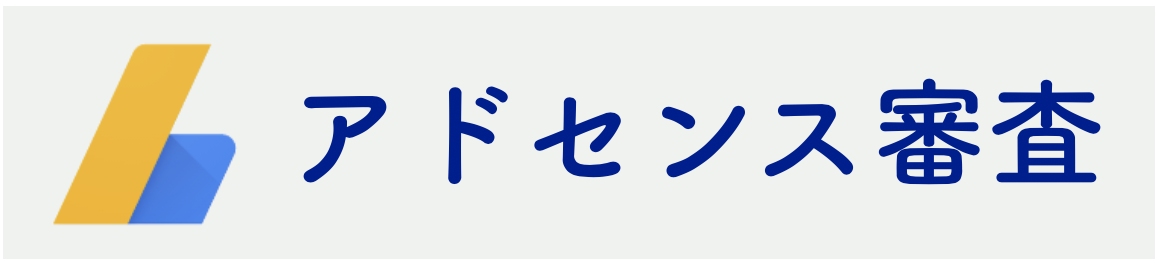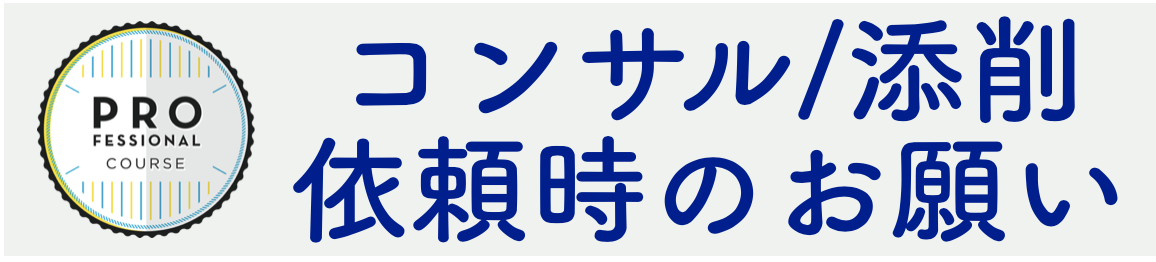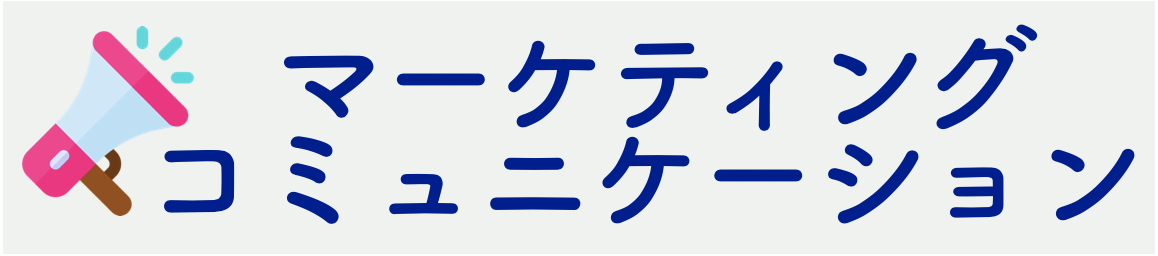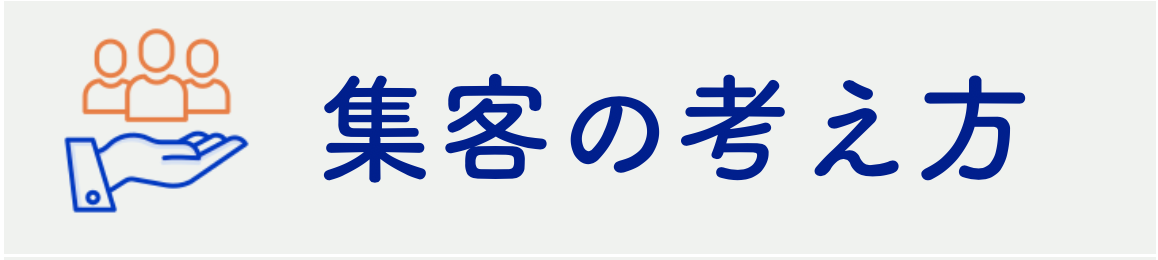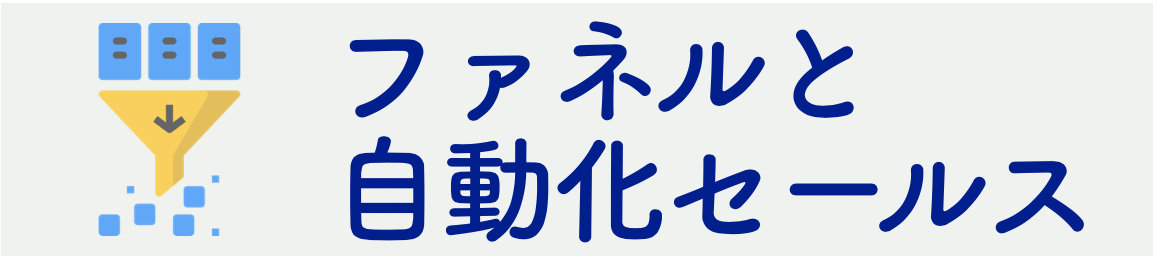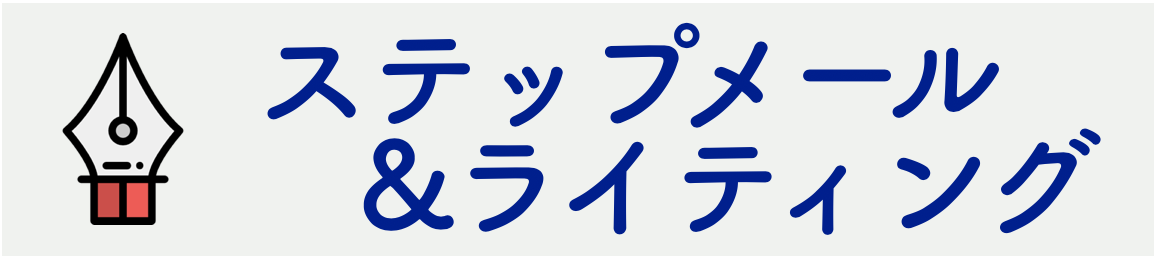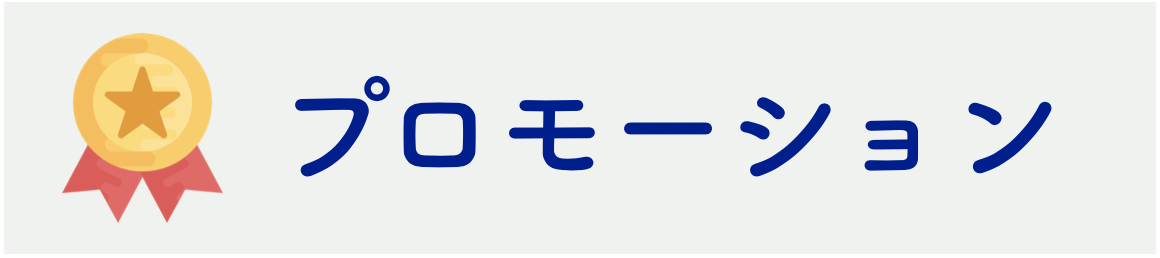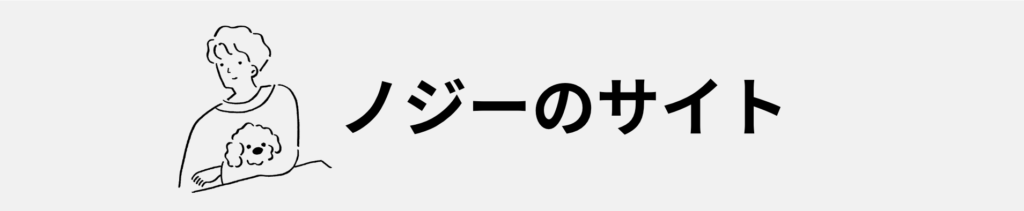ビジネスの基本は「価値提供」ということはよく耳にすると思いますが、そもそも「価値」に相対的な尺度というものはなく、個々人の考え方に基づくものであるということは、前提にしていきたいですね。
つまりAさんにとっては価値の高いものが、同様にBさんにとって価値のあるものであるとは限らないということです。
例えば、テレビのバラエティ番組を見て「こんなものはくだらない!」と撥ね付ける人もいれば、「毎週面白く見ていて、この番組があるから毎日仕事を頑張れる」という人もいるでしょう。
僕たちは「ビジネス」をしていくわけである以上、必然的に「価値提供をする」ということは避けて通れません。
それでは「価値が高いか低いか」とは誰が決めるかというと、価値の提供側ではなく、基本的には「受け手」になるわけですね。
もちろん、ビジネスを仕掛ける側として、本来価値のないものを「これは価値のあるものだ!」とブランディングして…ということも考えられますが、最終的にその対象の価値を決めるのは、情報の受け手です。
余談ですが、よく就職面接とかで「このボールペンを1万円で売ってください」という課題を与えられることもありますね。
繰り返しになりますが、価値を判断するのはあくまで受け手であり、提供する側ではありません。
よくブログだと「一次情報を元にした完全オリジナルなコンテンツじゃないと価値がない」的な意見を耳にすることもありましたが、それもある部分では間違っていて、あくまで価値があるかどうかを決めるのはコンテンツの受け取り手です。
仮に「ネットの情報をまとめただけ」だとしても、それがわかりやすくまとまっていて、訪問者のニーズを満たすものであれば「キュレーションサイト」として大きな価値になるケースも当然あるわけです。
NAVERまとめなんかは顕著ですよね。あとはグノシーのようなサイトとかも。
バイヤービジネスでも、日本ではなかなか買えない服や、数年前のモデルは高値で取引されますし、いわゆる「転売」という手法も大きな価値をもたらしたりするものです。
銀行預金もただ預かってもらうだけで、利子もほぼつかず、しかも自分のお金を引き出すために手数料がかかったりするわけですが、ほとんどの国民が銀行預金を活用してます。
これも「一見すると価値がなさそうなものに高い価値を感じる人がいる」ことの証…と言えるのではないでしょうか。
ということで、これからビジネスを行っていく以上は「価値」に対して寛容になることが大事で、自分の主観では受け入れることができないものに対しても「これはどんな価値があるのだろうか」と前向きに考える姿勢が大事ですね。
だから「興味がなくても流行は抑えておく」的な姿勢も大事だと思いますし、価値の多様性を認めることでこそ、マーケット感覚が鍛えられていきます。
逆に、自分の指標にとらわれすぎてしまうと、どうしてもビジネスセンスが高まっていかないので、世の中の全ての事象に価値があると考える癖をつけると、良いトレーニングになりますよ。