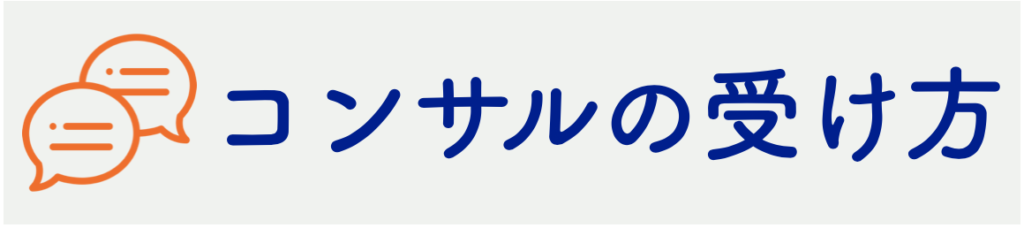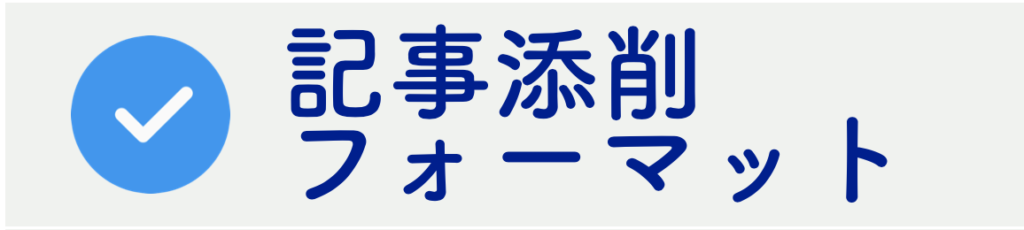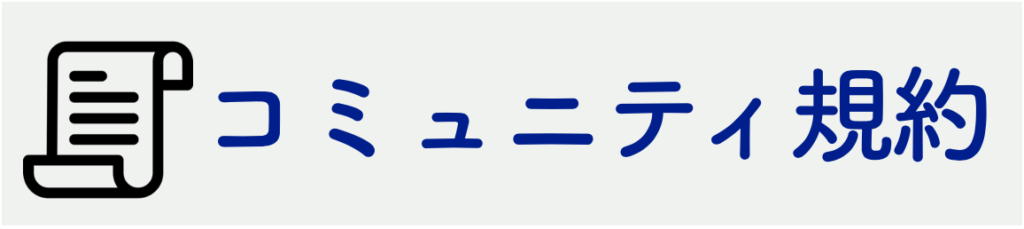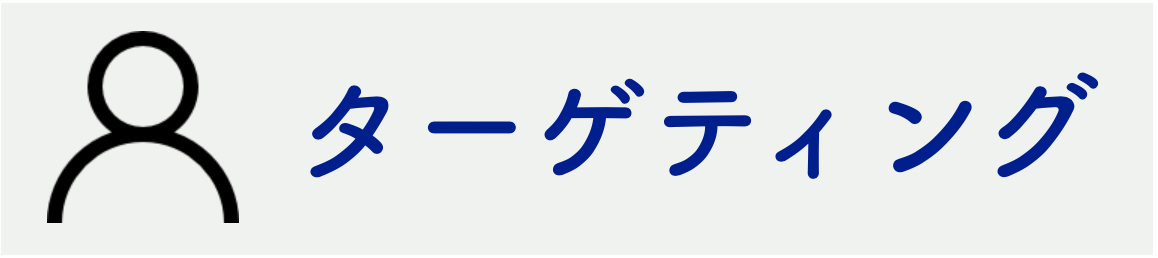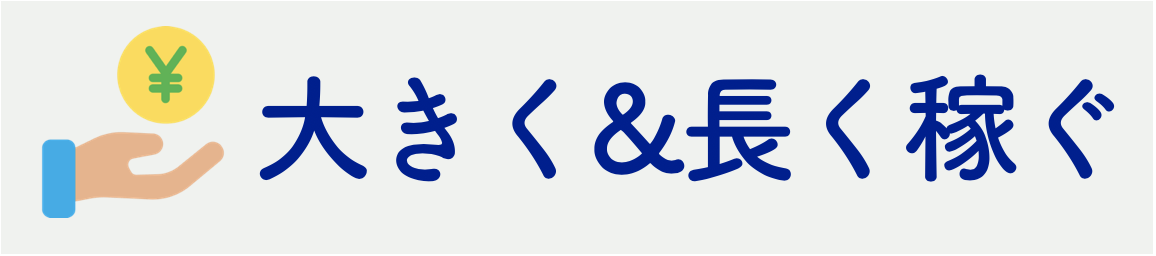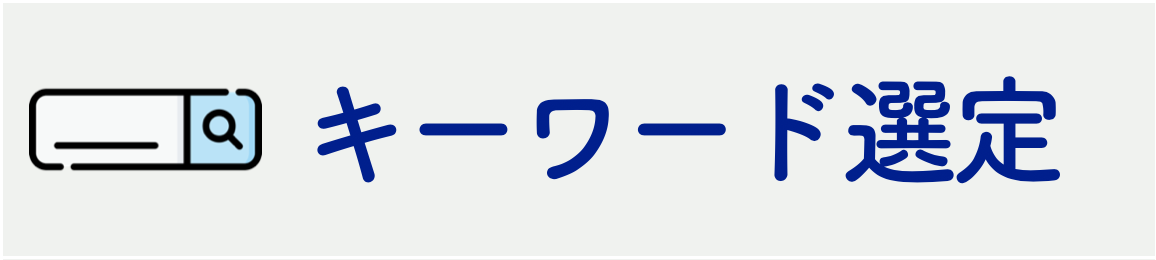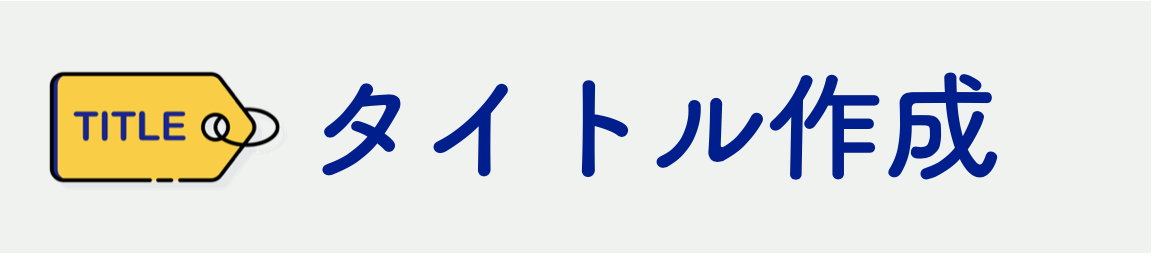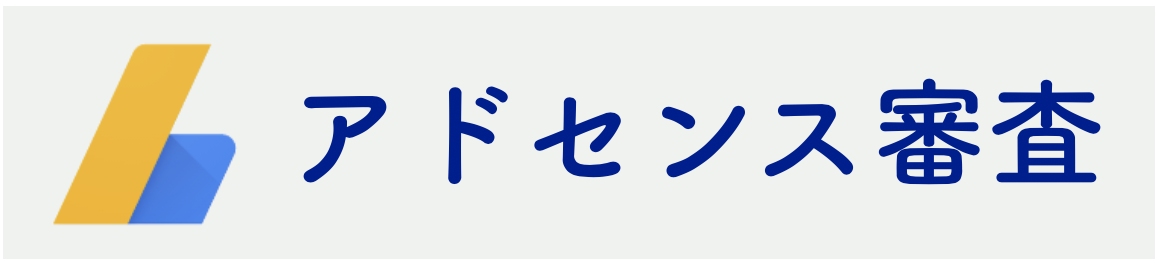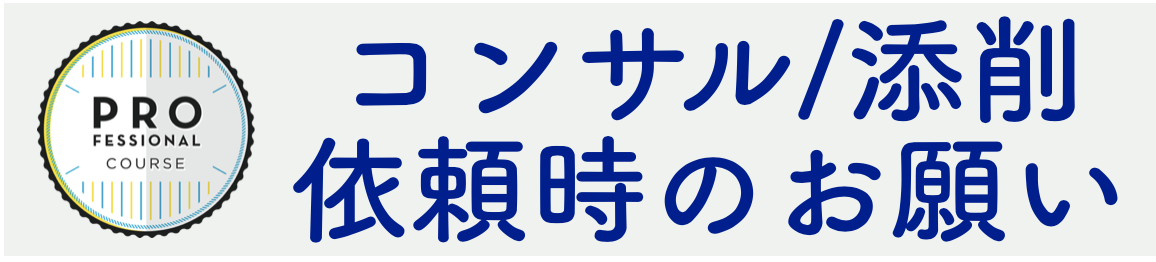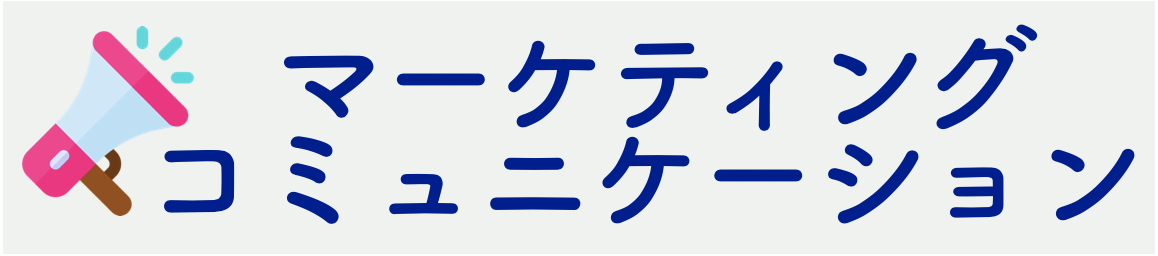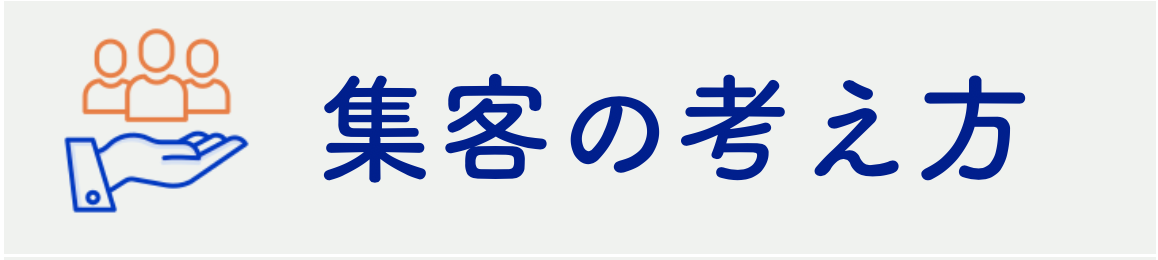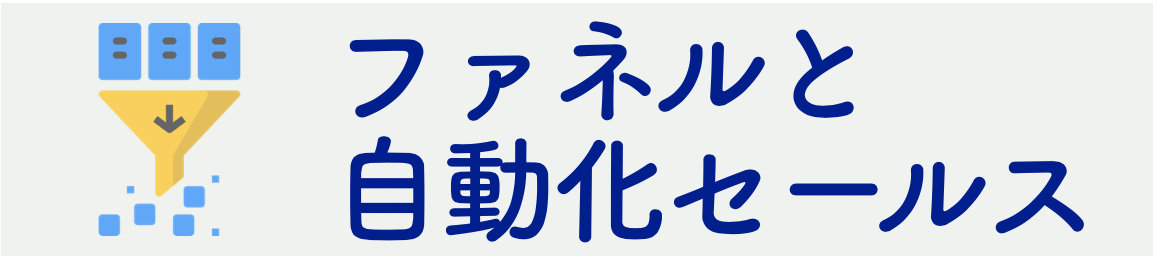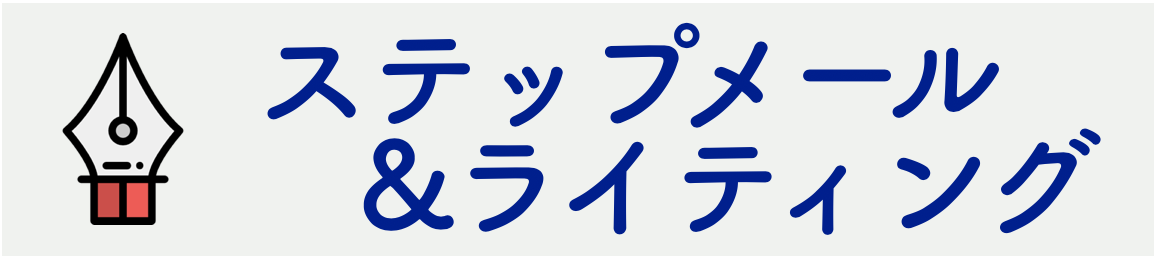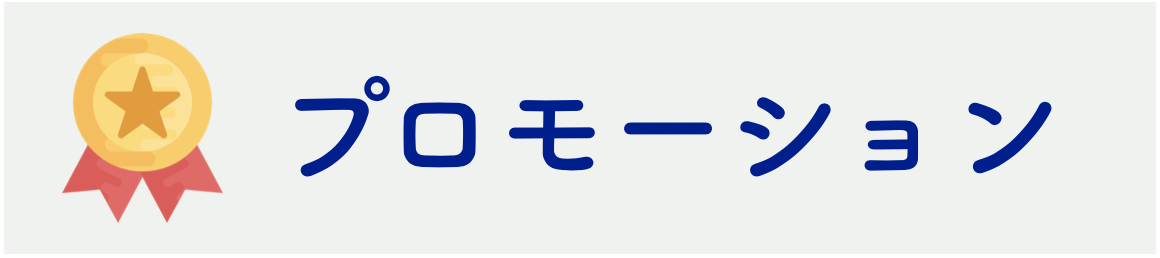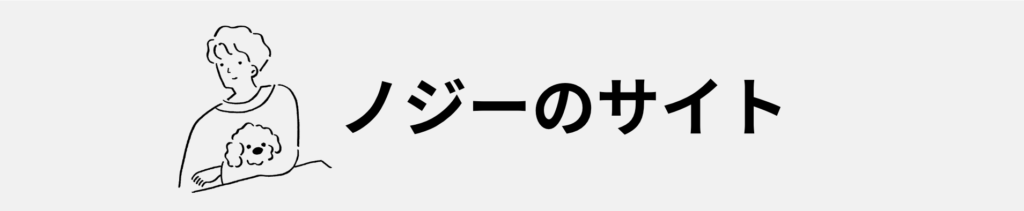ビジネスでは「モデリング」はとても大事ですが、表面を真似るのではなく、必ずその裏側にある本質をモデリングすることが大事です。
例えば、一時期Twitterで「続きはプロフで」とか「〜〜の理由は固ツイに書いてるんだけど」のようなツイートをして、固定ツイートやプロフィールに誘導して、LINE登録とかに誘導する方法がめちゃくちゃ流行りましたよね。
ただそれを表面だけ真似て、今から熱心にやってしまうと、ちょっと残念な印象が強くなってしまうでしょう。
なぜなら、あの手法はかなり一般化してしまい見飽きられてしまっているのと「どうせ、どこかのSNS塾とかがこぞって教えてるんでしょ?」みたいな目で見られるようになってしまったからですね。
そうなると最も本質的な部分である「140字で興味を惹かせて、プロフへ飛んでもらう」という効果がかなり薄くなってしまうわけです。
もう1つ例を出します。
皆さんのメルマガを添削していると、必ずと言っていいほど追伸欄に「課題」とか「ワーク」を載せていらっしゃいます。
僕が「これは何のためにやっているんですか?」と聞くと、皆さんこぞって「みんな同じようにしてるから」とか「そういうものだと思って」とお返事をされますね。(耳が痛くなったらすいません)
多分なんですけど、ステップメールの中で「ワークの時間」というものを設けたのは、toCのビジネス系発信者の中では僕が最初なんじゃないかなぁと記憶しています。
というのも、当時はみんな追伸欄で返信を促して、DRMの醍醐味である双方向コミュニケーションに持ち込むとか、あるいは一貫性の原理や単純接触効果による成約率アップを狙っていたんです。
ただ、それに加えて、メルマガを1つの「企画」とか「講座」っぽくして帰属意識を高めたいなと思ったので、「課題」的なものを出すことを決めて「課題」だと僕のブランディングっぽくないので「ワーク」という言葉を使うようにした…という次第です。
また「ワーク」的な見せ方をしている人は周りに誰もいなかったので、それを採用することで「この人は他と違うな」と思わせることも狙いの1つでした。
だから、みんながみんな「ワーク」をやり出すと、僕の狙いからは結構遠ざかっていってしまうわけですね(笑)
よく皆さん「周りがみんなこうやっているから、自分もこうした」ということを仰られますが、僕ならいかに「周りがやっていないことをやるか」を考えます。
もちろん周りがやっていないことをやると大コケするリスクはありますが、「何のためにやるか」という狙いの部分が合っていたり、本質的な部分さえ合致していれば、まず問題ありません。
だからこそ、モデリングをする際は表面上を真似るのではなく、その表面に至るまでの思考の部分を真似ていくことを大事にしていきましょう。